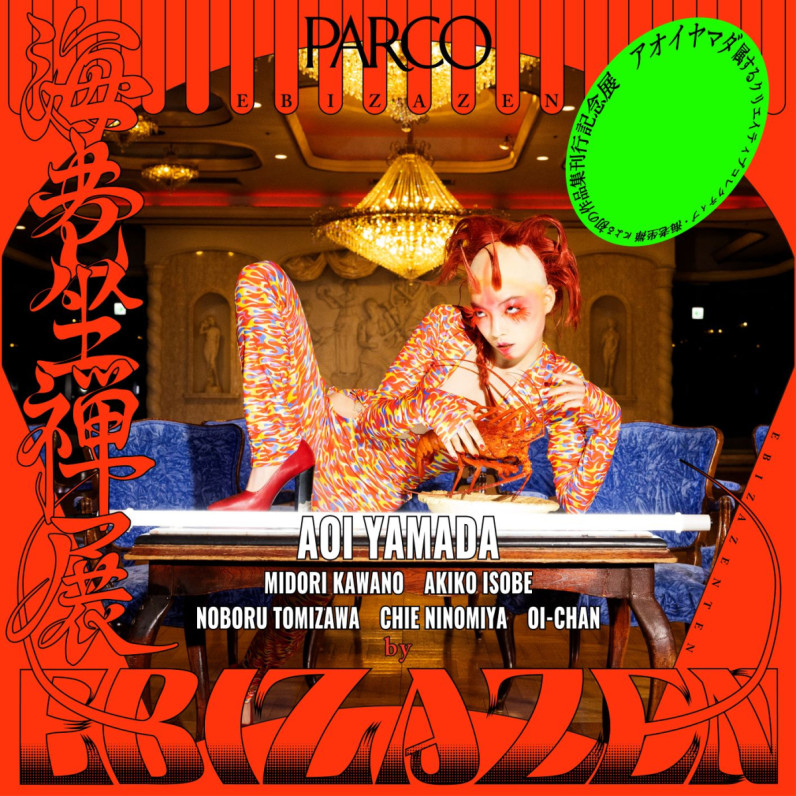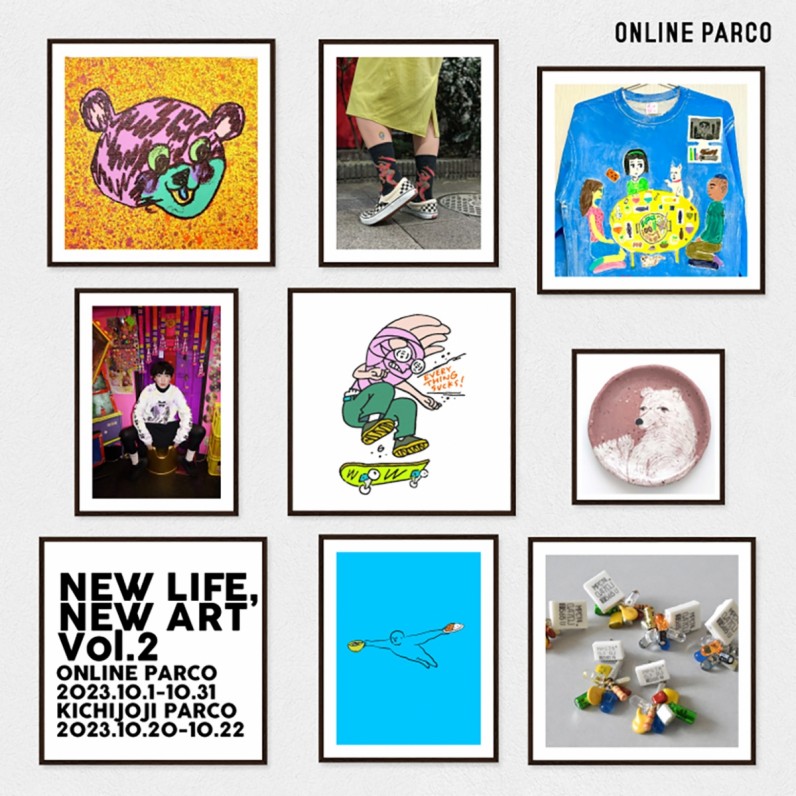さてさて、時代が進むに連れ、肖像画の権威性は薄れていきます。また、写真が発明されると、肖像画から肖像写真へとシフトしていきます。宝石をジャラジャラ身に付けていたファッションも、徐々にシンプルで親しみやすいものへ。

イギリス王室のパブリックイメージの変遷だけでなくファッションの変遷、メディアの変遷といったものを知ることができる展覧会となっています。
と、500年の歴史を辿るのも楽しみ方の一つですが、この展覧会にはさらなる楽しみ方があります。それは、肖像画に秘められたストーリーを“読み解く”というもの。作品のサイドには必ず、描かれた人物についての解説が用意されています。さらに、特に重要な人物に関しては、今展のナビゲーターである中野京子さんによるスペシャル解説も用意されています。それらの解説を読むことで、彼ら彼女らがグッと身近な存在に。どんな人生を歩んだのか。どんな性格だったのか。そういった人物像を知った上で観れば、作品の魅力は何倍にも何十倍にも膨れ上がります。
例えば、ヘンリー8世の肖像画。日本ではあまり馴染みのない人物ですね。

《ヘンリー8世》 King Henry VIII by Unidentified artist, after Hans Holbein the Younger, Probably 17th century(1536) ©National Portrait Gallery, London
何も知らないで見れば、ただのテンション低めのオジサマにしか見えないでしょう。そんなヘンリー8世ですが、あるヴェネツィアの外交官は、「今まで見てきた中で最もハンサムな君主だ」と称しているそうです(肖像画を見る限り、そこまでイケメンな感じはしませんが・・・)。実際、かなりのプレイボーイだったそうで、生涯に6回も結婚をしています。結婚するも飽きると、すぐに浮気。そして、離婚するというのが、彼のパターンだったそう。離婚で済めばまだいいほうで、妻だった女性を処刑することもありました。それも2回も。そういったことを知った上で、改めて作品を観てみると、ヘンリー8世の内側にある静かな狂気のようなものが見えてきませんか?
また例えば、アン女王。エリザベス1世以降初の女王です。

《アン女王》 Queen Anne by Sir Godfrey Kneller, Bt (ca. 1690) ©National Portrait Gallery, London
この頃は、こんなにもスリムなスタイルですが、ストレスから暴食するようになり、戴冠式の際は肥満と痛風のため歩くことができず、輿に乗って行進したのだとか。また、アルコールにも走り、後年は『ブランディおばあちゃん』というあだ名が付いていたとのこと。誰もが一度は羨む王室の生活。しかし、そのストレスはハンパないのですね。やっぱり普通の生活が一番。そんなことをアン女王は教えてくれます。